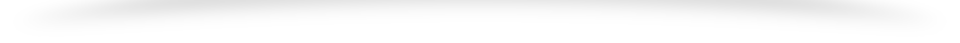まず結論(30秒でわかる)
-
在職老齢年金=働きながら年金を受け取る人のための“調整”制度。給料+年金が多いと一部カットされます。Ministry of Health, Labour and Welfare
-
いま(2025年度)は、給料(総報酬)+年金=51万円まではカットなし。超えた分の半分がカット。Nenkin+1
-
2026年4月からは、基準が62万円に引き上げ。つまり、今よりカットされにくくなる。Ministry of Health, Labour and Welfare+1
在職老齢年金ってなに?
「年金受け取り+お給料」が一定額を超えると、老齢厚生年金の一部を一時的に止めますよ、という“ルール”。
制度の目的は「たくさん稼いでいる月は、年金はちょっと控えめに」という調整です。Ministry of Health, Labour and Welfare
“いまの基準”と“これから”を一枚で
-
2025年度の計算
合計(基本月額=年金の月額/12 + 総報酬月額相当額)が51万円以下→全額支給。
51万円超→超えた分の1/2だけカット。Nenkin -
2026年4月から
この基準額が62万円にアップ。62万円まではカットなし。Ministry of Health, Labour and Welfare
例)給料+年金=55万円の月
2025年度:55−51=4万円 → 2万円カット
2026年4月以降:62万円までOK → カット0(同条件なら) Ministry of Health, Labour and Welfare
「総報酬月額相当額」って何が入るの?
カンタンにいうと、**毎月の標準報酬月額+(直近1年の賞与÷12)**です。
標準報酬月額には、基本給・残業代・通勤手当などの“お給料としての手当”が入ります。Nenkin+2Nenkin+2
カットの対象になるもの(代表例)
カットの対象にならないもの(代表例)
-
厚生年金に加入していない別バイトの収入(=標準報酬に載らない)
-
個人事業の利益・不動産収入・配当や運用益 などの給与以外の所得(=総報酬の定義外)
※「総報酬月額相当額」は標準報酬月額+標準賞与額ベースなので、給与以外の所得は含めないという整理です。詳細は最寄りの年金事務所へ確認を。Nenkin
過去→現在→これから(時系列で把握)
-
〜2022年3月:60〜64歳は28万円基準、65歳以上は47万円基準で別ルール。Nenkin
-
2022年4月〜:47万円に統一(60〜64も65歳以上と同じ考え方に)。Nenkin+1
-
2024年度:物価等での見直しにより50万円が目安。Ministry of Health, Labour and Welfare
-
2025年度:51万円。いまここ。Nenkin
-
2026年4月〜:62万円に引き上げ(法改正成立済)。Ministry of Health, Labour and Welfare+1
サクッと自己診断(電卓いらずの3ステップ)
-
年金の月額(老齢厚生年金の報酬比例部分/年額を12で割る)をメモ。Nenkin
-
給料の標準報酬月額+(直近1年の賞与÷12)=総報酬月額相当額をメモ。Nenkin
-
1)+2) が
- 2025年度:51万円以下 → カットなし
- 超えたら → 超過額の1/2がカット
- 2026年4月以降は62万円基準で再チェック!Nenkin+1
よくある質問(1行回答でスッキリ)
Q. 65歳未満と以上で違うの?
A. 今は同じ式で計算(2022年に統一)。Nenkin
Q. 交通費はどう扱う?
A. 通勤手当は“報酬”に含む=総報酬に入ります。Nenkin
Q. うちは年2回ボーナス、どう数える?
A. 1年分の賞与を12で割って月額に足します。Nenkin
Q. 2026年4月って本当に上がる?
A. 法改正が成立。62万円へ引き上げ予定と厚労省が案内。Ministry of Health, Labour and Welfare
今日やること(チェックリストでコピペOK)
-
自分の老齢厚生年金の月額(報酬比例)を確認した
-
**標準報酬月額+(直近1年の賞与÷12)**を出した
-
合計が2025年度は51万円、2026年4月以降は62万円を超えるかチェックした
-
通勤手当も含めることを忘れていない(=総報酬に入る)
-
境目に近い人は、2026年4月からの影響も試算した
さいごに(超要点)
-
2025年度:51万円、2026年4月〜:62万円。ここだけ覚えればOK。Nenkin+1
-
計算は**「年金の月額」+「総報酬(月給+ボーナス÷12)」。超えた分の半分**がカット。Nenkin
-
何が“総報酬”に入るか迷ったら、年金機構の定義を確認。Nenkin+1
制度は年度で数値が更新されることがあります。最終確認は日本年金機構・年金事務所の公式情報をご覧ください。